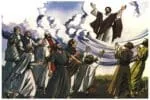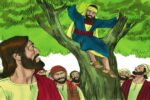わかりやすい聖書入門サイト、やさしい聖書解説で独学でシンプルに深く学ぶキリスト教サイトです。特定の教派や教団に囚われないで、主イエス様の教えに耳を傾け霊的に成長していきましょう。聖霊なる神様が読者の皆様を導いてくださり、信仰が深められますようにお祈りします。
主イエス様は、あなたを学びの場へと招いています。主イエス様に学び倣いましょう。人生の生き方を、主イエス様は私たちに教えてくださっています。必ず、あなたの人間性が変えられます。主イエス様が、聖書の言葉を通して、聖霊を通して、あなたを変えてくださいます。読者の皆様の生活に少しでもお役に立てれば幸いです。

最近の投稿

聖書解説 野口良哉伝道者の投稿
コメントは管理人が承認した後に表示されます。承認後にコメントは表示されます。